動画編集の代行、YouTubeへの出演依頼、企業案件など、YouTuberは、様々な場面で契約を締結することになります。
そこで今回は、前編と後編に分けて、契約の基本についてご説明します。
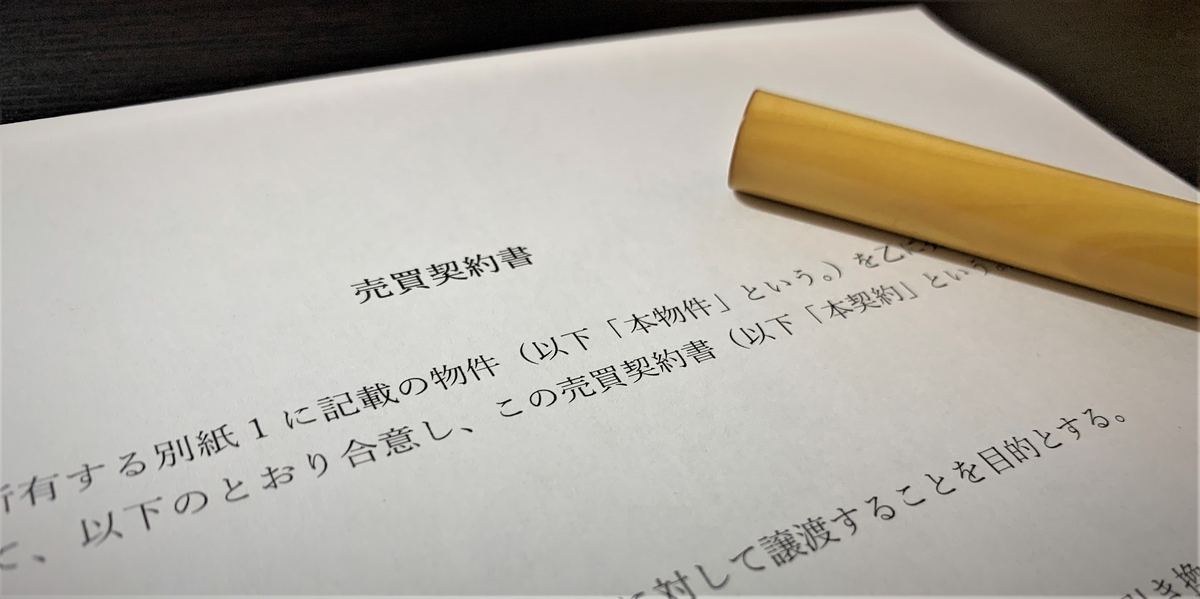
そもそも「契約」とは?
契約とは、法的な拘束力を持つ当事者間の約束のことを指します。
言い換えると、当事者間の約束のうち、客観的に見て、法的に拘束することが予定されているようなものが、契約になります。
お金が絡んでくるような約束は、基本的に契約と言えるでしょう。
契約に該当しない約束の例としては、友達同士の遊ぶ約束などが挙げられます。例えば、「明日12時にカフェに行こう」と約束したとしても、それは客観的にみて、法的な拘束が予定されたような約束ではありません。
口約束は法的に契約として認められるの?
契約は、申込と承諾の合致により成立するもので、契約書を作成しなかった場合でも、原則として法的に有効に成立します。
例外的に、保証契約など、書面によって契約することが法律上定められているものもありますが、原則として、契約書の作成は契約の成立のために必要なものではありません。
例えば、コンビニで飲み物を買う場合、コンビニと顧客との間で契約書を交わすことはありませんが、売買契約が成立しています。
なぜ契約書を作成するの?
ではなぜ契約書を作成するのでしょうか。
契約書を作成することの意義は、大きく3つあります。
①証拠としての機能
②紛争の予防機能
③リスクのコントロール機能
①証拠としての機能
契約は、口約束でも成立しますが、口約束で済ませてしまうと、記憶違いや、後で契約した事実や契約内容を忘れてしまうことがあります。
そこで、契約書を作成し、書面の形で残しておくと、合意をしたかどうか、どのような内容で合意したかを当事者間で明確にすることができます。
また、当事者間で、争いになった場合、第三者である裁判所に判断をしてもらうことになりますが、裁判所は、両者間で契約が締結されたかどうかを知る由もなく、当事者から提出された証拠から事実を認定するほかありません。
そのため、裁判となった場合には、契約締結の事実や、契約内容について立証するための証拠を提出しなければなりませんが、契約書を作成していれば、契約書の原本を証拠として提出することができます。
そのため、「証拠として」契約書を作成するわけです。
②紛争の予防機能
とはいえ、裁判所にまで行くケースは、さほど多くはないかもしれません。
そんな場合でも、契約書には重要な意味があり、それが紛争予防です。
まず、①とも被りますが、口約束の場合、合意をしたかどうかや、どのような内容の合意をしたのかが曖昧になってしまいます。
記憶違いが起きた場合、契約書がないと、どちらが正しいのかがわからなくなってしまいます。また、時の経過とともに人の記憶は薄れてしまうため、時間がたてばたつほど認識違いが生じるリスクが大きくなっていきます。
認識違いが生じた場合でも、ビジネスがうまくいき、両者不満なく物事が進んでいればまだよいですが、いったん環境や関係性が悪化してしまうと、一気に紛争化してしまうリスクが高まります。
契約書の形にしておけば、何をどのように合意したのかが明らかになるため、このような無用な紛争を避けることができます。
また、通常契約書には、様々な法的リスクについて、それが生じたときの取り扱いを明確に規定します。
そのため、何かトラブルが起きた場合でも、その都度もめることなく、契約書に従って物事を処理することができるようになります。
ビジネスの場面は、基本的にはWinWinの関係です。
取引において、何かトラブルが起きてしまった場合に、契約書に従い、あらかじめ両当事者間で合意した通りの処理をすることができれば、トラブルにならずに済むため、良好な関係性を維持することができ、今後の取引にも良い影響を与えることになります。
③リスクのコントロール機能
想定されるトラブル等について、あらかじめその処理方法や、損害賠償の上限額などを定めておくことで、ビジネス上のリスクをコントロールすることができます。
例えば、「何か問題があったときでも、金銭は支払わない」とか、「損害が生じた場合でも、売買代金の1割を上限とする」など、責任範囲を限定することで、ビジネス上の金銭的リスクを明確化できれば、重要な意義を有する契約であればあるほど、その経営上の意義も大きくなるでしょう。
契約書にはとりあえずサインしておいたほうがいい?
上記の通り、契約書は、裁判になった際だけでなく、裁判に至らないために有意義なものです。
そうであるなら、相手から契約書へのサインを要求されたら、断らずにとりあえずサインしておいたほうが良いのでしょうか?
答えは、Noです。
先ほど記載した通り、契約を締結すると、何かトラブルが起きてしまった場合に、契約書に従って処理することになります。
相手方が提示してきた契約書は、基本的には、相手に有利な内容になっています。
そのため、何も読まずにサインしてしまうと、自分に不利益な条件に、法的に拘束されてしまうことになりかねません。
例えば、次の事例を見てみましょう。
Aさんは、山梨県に転勤することになったため、東京にある築20年の一戸建てを売却し、山梨県の一戸建てを購入することを検討していました。Aさんが物件を探していると、Bさんが売りに出している山梨県の一戸建てを見つけました。話をしてみると、ちょうどBさんは、東京の一戸建てを購入しているとのことで、Bさんは、Aさんの所有する一戸建てを気に入ってくれました。AさんとBさんは、それぞれ相手の物件を1000万円で購入することに決めました。
Bさんは、①AさんがBさんから物件を購入する契約書と、②BさんがAさんから物件を購入する契約書を作成し、Aさんに渡しました。Aさんは法律のことをよく知らなかったので、売買対象の物件が正しく記載されているかという点と、売買代金の部分だけ確認して、サインしました。
その後、AさんとBさんは、それぞれ購入した家で暮らし始めましたが、それぞれの家に欠陥があることがわかりました。その修繕には、それぞれ200万円がかかります。
①の契約書には、建物に欠陥があった場合でも、Bさんが損害賠償義務を負わないと規定されていましたが、②の契約書には、建物に欠陥があった場合には、その修繕に必要な費用を全額Aさんが負担すると規定されていました。
この場合、AさんはBさんに対して200万円を支払わなければなりませんが、BさんはAさんに対して金銭を支払う義務は生じません。
そして、Aさんとしては、契約書にサインしてしまっている以上、上記に従わざるを得ません。
一見不公平なようですが、あくまでも公平な当事者間での取り決めであり、裁判になったとしても、Aさんは負けてしまうでしょう。
このように、一見問題の無いように見える契約書でも、よく読んでみると、相手に有利な規定となっていることは良くあります。
契約書に何が記載してあるのかをきっちり読むことが重要になりますし、重要な契約書となれば、弁護士に相談することも大切になってくるわけです。
後編では、法的には契約書にハンコを押す必要があるのかといった点や、契約書作成時に弁護士に確認してもらう理由などをご説明しますので、ぜひ 後編の記事もご覧ください。